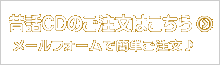新潟県長岡市(旧三島郡越路町)の高橋ハナさんの昔話。昔話独特の語り調子と、いきいきしたリズムが分かるとお話が語り始めます。ぜひCDでむかしばなしを聞いてみてください。
ヘビの恩返し(動物の報恩)
あったてんがの。
あにが山へ行くといって出かけたと。
途中に子どもが大勢でヘビをつかめて殺そうとしていたと。
あにがそれを見て
「ねらねら、そんげのヘビ殺すなや」
とようたと。子どもは
「このヘビ、ちんこいろも耳があるんだんが、殺そてがら」
とようたと。あには
「ねら、おれにこのヘビ売ってくれ」
とようたと。
子どもは銭が欲しいんだんが、売ったと。
あには、ヘビ買うて遠くへ持っていって
「ほら、命のないどこ助けてやったんだんが、子どもの目につかんように遠くへいげ」
とようて逃がしたと。
それから幾日かたって、あにが山からあがってきたら、後ろから若い女がついてきたと。あにに
「道に迷うて、暗くなってしもうたんだんが、一晩泊めてくらっしゃい」
と頼んだと。あには
「おらうちは貧乏で何にもないが、それで良かったら泊まらっしゃい」
と泊めてやったと。
一晩泊めてやると、つぐの朝、女が「おれをここの嫁にしてくんねか」
と頼むがんだと。あには
「こんげの貧乏なうちで良かったら、なじょうも嫁になってくれ」
とようたと。
嫁になって一年もめると、嫁に子どもが生まれることになったと。
嫁はあにに
「子どもが生まれるすけ、ちんこい小屋作ってくれ」
と頼んだと。あにが小屋作ってくれたと。嫁は
「おれが達者になってくるまで小屋の中、決して見ねでくれ」
と頼んでちんこいたらい一つ持って小屋へ行ったと。
あには、見るなとようたが、見たくてどうしょうもねんだんが、小屋を作る時ちゃんと穴ひとつ開けておいたと。
そこへ行ってのぞいてみたら、女が大ヘビになってわぐらをかいて(とぐろを巻いて)その真ん中に子どもをチョコンと乗せていたと。
あにはそれを見てたまげて(おどろいて)うちへきたと。
嫁が達者になって子をぶうて(背負って)きたと。
うちへ来てみると、あにの顔色が悪いんだんが、わかったと思い
「あに、おれは、おまえに助けてもらったヘビだ。おまえに恩返ししようと思って来たがだ。見られてしもうたんだんが、これでうちへ帰る」
とようたと。あにが
「おまえがいのうなったら(いなくなったら)、この子どうして育てる」
とようたと。嫁は
「おれが目玉をやるすけ、子が腹すかせたら、しゃぶらせてくれ」
とようて目玉をとって置いていったと。ほうして
「おれは、大津の三井寺の池にいるすけ、困ったことがあったら、いつでも来てくれ」
とようて行ってしもうたと。
子どもは目玉をしゃぶってでっかくなったと。
ある日、目玉を縁側に出して遊んでいたら、カラスがきて目玉をくわえていってしもうたと。
あにが困ってしもうて、子どもぶうてかかのいる池へ来て、
「かかあ」
とよばったら、かかがヘビになって出てきたと。
あにが「子どもがおっかんがる(恐ろしがる)すけ、元の姿で出てきてくれや」
とようたら、こんどは元のメッコのかかが出てきたと。
これこれこういう訳で来たとようたら、かかはもう一つの目玉を取ってくれたと。あにが
「おまえ、めくらになって困るだろう」
とようたら、かかが
「大津の三井寺の釣鐘を寄付してくれ。そうせや、鐘の音で今何時だろうと思うているすけ」
とようんだんが、あにが釣鐘を寄付したと。
その鐘がばかいい音たてるんだんが、弁慶がその鐘を比叡山の山の上に持っていってはたいたと。
ほうしたらばかいい音がして、ひとの耳には、ゴーンと聞こえるろも、弁慶の耳には、かえろ、かえろと聞こえたと。
弁慶が怒って山の上から下の谷に投げ落としたと。
ほうして、弁慶が降りていってみたら、鐘がザクザクに壊れていたと。
いい気味だと思ってうちにきて、つぐの朝げ行ってみたら、元通りにくっついていたと。
弁慶は、これは、当たり前の鐘ではないと三井寺へ納めたと。
池の中のかかがヘビになって出てきてなめてくっつけたと。
いきがさけた。
……読み比べてみたい昔話
共に<動物の報恩>をテーマとしたお話です。