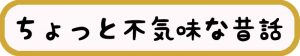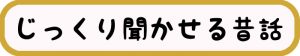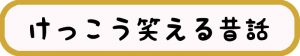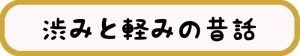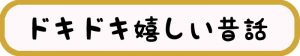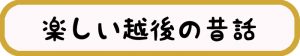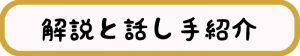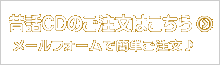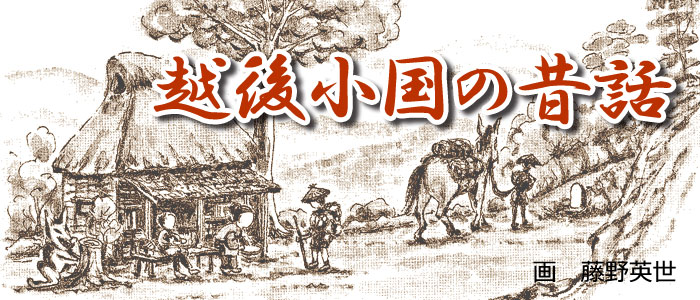
十二支(じゅうにし)の順番
新潟県長岡市(旧刈羽郡小国町)の昔話。どこか人なつっこい方言とおだやかな語り口調が嬉しい昔語りです。昔話のCDで独特の語り口調がわかると民話の文章が話し始めます。ぜひ昔ばなしを地の語りで聞いてみてください。
むかしあったてんがの。
太郎兵衛の家は身上(しんしょう)がいいんだんが(身上がいい=金持ち)、ねこもまたまいんち、まいんち魚いっぺいもろうて、ねずみなんて見向きもしねえてんがの。
次郎兵衛の家は、牛と爺さまが住んでいるろも、びっぼれ、爺さまも牛も食いもんがなくて、痩せこけて腰も立たんようになったと。
太郎兵衛の家じゃあ、ねずみもねこにつかまらんねえし、倉の中は、こめも豆もいっぺえある。
ねずみの親方が
「次郎兵衛の爺さまと牛が可愛そうらすけ、食いもん持っていってやろうねか」
ということで、ねずみが毎日毎日、今日は米、明日は豆とあつきと、牛んどこへ運んで食わしたと。
ほうしたら爺さまも牛も丸まると肥えて、足腰がたっしょ(達者)になったと。
ちょうどその頃、お寺の方丈様が十二支を集めて干支(えと)を作るんだんが、明後日(あさって)の日の出と一緒に、お寺の門を入ったものを十二支の仲間にしるというお触れを出したと。
そこで、ねこは
「おらやらやら、あさげのさぶいがんに十二支なんて、仲間にしてもろうわんたっていい」
そう言うて、いるてんがの。ねずみは
「おら小さくて跳ばんねすけ、仲間にしてもらわんねえ」
とあきらめているてんがの。
となん(隣り)の爺さまと牛は
「こんだおらが恩返ししる番だ」
そういうてねずみを牛の角につかまらして、日の出と一緒に、お寺の門に飛び込んだと。
本堂の方丈様めがけて、ぐーんと投げ飛ばしたら、ねずみは方丈様のほうへすぽんと飛び込んだと。
ほうして、十二支の順番を決めるろき、ねずみは牛どんが先らというし、牛はねずみどんが先らというて遠慮しおうたんだんが、方丈様は、
「なかなかいい心掛けだ」と褒めてくれ、
「こっだのろきは牛どんが先になるがんに、今はねずみどんが先の方がいいねか」
ということで、
「ねうし」
と干支の順番が決まったらあと。
のめしこき(怠け者)のねこは仲間にしてもらわんねかったと。
いきがぽんとさけた。
武石 鈴木百合子
……もっと読んでみたい昔話