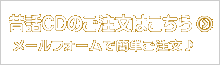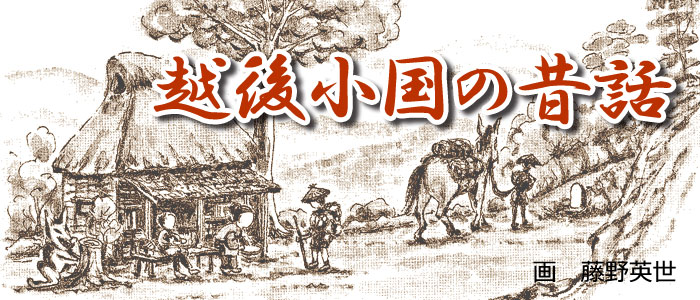
『越後小国の昔話集』解説
新潟県長岡市(旧刈羽郡小国町)の昔話。どこか人なつっこい方言とおだやかな語り口調が嬉しい昔語りです。昔話のCDで独特の語り口調がわかると民話の文章が話し始めます。ぜひ昔ばなしを地の語りで聞いてみてください。
資料として昔話を集めて本にまとめれば終りだという考えから、語ることによって昔話を次の世代に残そうとする動きへ
『榎峠のおおかみ退治―越後小国の昔話集』解説
高橋 実
はじめに
新潟県小国町は、新潟県のやや南に位置し、中越の中心都市長岡、柏崎、小千谷を結ぶ三角形の底辺の中心に位置している。かっては、豪雪過疎の出稼ぎ地帯であった。稲作が町の基幹産業だったが、冬季の道路も確保され、除雪体制が整備されて、今は、近隣三市に通勤している人が多い。合併当時の昭和三十一年には人口一万八千人だったが、少子高齢化が進み、平成十二年初めの今は八千人を割ってしまった。
収載された三冊の本
さて、この町の昔話七十四話を集めてこの本となった。しかし、ここに載せられている昔話は、同じ時期に集められたわけではない。昭和三十年代から平成まで四十年の年月の隔たりがある。
というのも、この昔話集には、活字になった次の書物や雑誌が元になっているのである。
古いのは私が高校三年から大学一年にかけて集めたガリ版刷り冊子「小国の昔話その一」である。昭和三十三年から四年にかけて集めた話である。当時、長岡の水沢謙一氏が県内の昔話を集めてブームになっていた。それに刺激されて、高校生だった私が町内(当時まだ町制がしかれていなかった)を回って集めたのである。三十五年にB五版四七ページを発行して町内の小学校に寄贈した。ここに収録した昔話は二八話だった。
この冊子が、それから二十五年経って、日本民話の会で民話学校を小国で開くことになって、見直される事になった。昭和六十二年、「民話の手帖」第三十二号(口絵写真参照)で「越後小国の昔話」の特集が組まれて、そこに私の集めた二十八話がそっくり再録されることになった。さらにそれに加えて、私の手元にノートのまま残されていた二十話も載せて合計四十八話が収録されている。本書の大部分はその時の昔話で占められている。
二番目は、昭和五十年三月、小国町教育委員会発行の「とんとむかし 小国の昔話.伝説 第一集」(口絵写真参照)である。これは町内の社会科の先生方が、町内に残る昔話を集めて本に纏めたものである。B五版十三ページの冊子には、八話の話が収録されている。これは第四集まで発行されているが、第二集は伝説。第三集は俗信、第四集は童歌となっている。
三番目は、「へんなか」第六号、特集「小国の昔話」(口絵写真参照)である。このころ、昔話の語りが見直され、芸術村フェスティバルなどで語りの会が開かれた。このときの話がここに十一話載せられている。
大久保ヨネさん、北原勲さん、鈴木百合子さんは、最近になって自分のノートに書き留めておいたものを私が見せてもらい、今回で初めて活字化されることになった。鈴木さん、北原さんなど昭和生まれである。
「小国の昔話」に語ってくれた話者はほとんど明治二十年代の生れであった。昭和生まれの人より四十年以上の開きがある。
「へんなか」には座談会「昔話の背景」があり、「民話の手帖」には、「民話と村おこし」の座談会が載っている。
本書は、この三冊を出典として類話があればこれを集めて、編集した。編集にあたって標題を変えたところもある。また類似の話は省略した物もある。
標題について
この本の標題は「榎峠のおおかみ退治」とした。これは「とんとむかし」で山野田の牧野スミさんが語った昔話である。榎峠は小国町と柏崎市・川西町の境界にある峠で、かって三国峠から柏崎に出る重要な峠だった。ここに大きな榎が立っていて、小学生の頃の遠足コースでもあった。そのすぐ傍に小国芸術村のある山野田集落が存在する。この話は永見恒太さんも知っていて、その話はおおかみ退治ではなくて、むじな退治だったという。小国の重要な峠の地名が入り、終りの部分は山崎氏の語る「まつきち」に似ているところがあるので、小国昔話のシンボル的な話としてこれを標題にした。